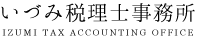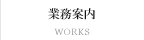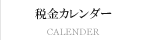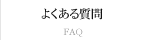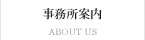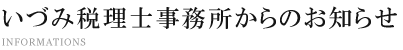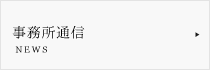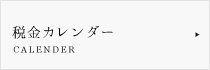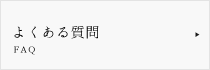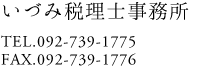2024/11/15
![]()
令和6年分年末調整 年調減税事務
前月の記事では令和6年分の年末調整関係書類の変更点についてお伝えしました。令和6年の年末調整では、定額減税の処理も必要となります(年調減税事務)。年末調整時点の定額減税の額を「年調減税額」といい、年調減税額を算出して年調所得税額から控除します。今回は年調減税事務の手順についてお伝えします。
1.対象者の確認
(1)「本人」の判定~年末調整の際に年調減税事務の対象となる人
年末調整の対象となる人が、原則として年調減税事務の対象者です。ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
(2)「扶養している家族」の判定~何人分が控除できるか
配偶者については「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」、扶養親族については「扶養控除等(異動)申告書」から把握することができます。
2.年調減税額の計算
年調減税額は「本人3万円」と「扶養している家族1人につき3万円」の合計額です。
3.年調減税額の控除
年調減税額の控除は、住宅借入⾦等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入⾦等特別控除後の所得税額を限度に⾏います。上記のとおり通常の例により年末調整を⾏い、令和6年分源泉徴収簿の「年調所得税額㉔」欄を算出し、年調所得税額から年調減税額の控除を行います。年調減税額を控除した後の⾦額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を算出した上で、過不⾜額の精算を⾏います。
4.源泉徴収票への表示
年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった⾦額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。
2024/10/11
![]()
令和6年分の年末調整関係書類の変更点が国税庁より公表されました。主な変更点をお伝えします。
1.主な変更内容
(1)追加事項
マル基・配・所の用紙に「年末調整に係る定額減税のための申告書」が加わり、用紙の名前が長くなりました。
基礎控除申告書と、配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書に年末調整で適用する定額減税の記載欄が追加されました。
↑基礎控除申告書
↑配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書
(2)削除事項
マル保の用紙に、これまで記載されていた「あなたとの続柄」の欄がすべて削除されました。
2.簡易な申告書(マル扶)
(1)簡易な申告書
源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させるという観点から簡易な申告書が創設されました。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出するマル扶から提出できます。
(2)異動の有無の判定
氏名の変更、住所又は居所の移転、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の変動、寡夫や障碍者などの該当又は非該当、年齢の変動による控除区分の変動などが異動の有無の判定に関わってくるものです。
判定により異動がないとされれば、簡易な申告書を提出することができます。
(3)記載事項
簡易な申告書の記載事項は、申告書を提出する本人の、氏名・住所又は居所・マイナンバー(記載不要の場合は不要)・前年から異動がない旨のチェックとなっています。
※下図の水色の部分が記載事項となります。
※上記申告書は簡易対応様式のマル扶ですが、通常のマル扶でも簡易な申告書を提出することができます。そのため通常のマル扶のレイアウトが変更されています。
(4)書類の保存
簡易な申告書はその提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。前年の記載内容から異動がないかの確認のために、連年簡易な申告書の提出を受けたような場合には、最後に提出を受けた簡易な申告書以外のマル扶の内容が確認できるようにしておくことに注意が必要となります。
2024/09/12
![]()
空き家の譲渡所得の3,000万円控除
1.特例措置の概要
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(以下、空き家特例)とは、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるものです。この特例措置は、令和5年度税制改正により、適用期間が令和9年12月31日までに延長され、特例の対象となる譲渡について拡充が行われました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
2.令和6年度以後の譲渡から買主側の耐震改修・除却工事でも特例対象に
令和6年1月1日以後の譲渡については、譲渡前に相続人(売主)が耐震改修工事や除却工事を行う場合に加え、譲渡後に“買主が行う場合”も空き家特例の対象となりました。買主による工事等は、譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までに完了する必要があります。
売主が、買主による工事で空き家特例の適用を受ける場合も、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、確認書)の添付が必要です。
家屋所在地の市区町村で確認書の交付申請を行う際、“買主に取得してもらう一定の書類”の提出が求められます。一定の書類について、耐震改修の場合は、「耐震基準適合日等の確認書類(耐震基準適合証明書、工事請負契約書のコピー、工事費用の領収書等など)」が当たり、除却等の場合は、「家屋全部の取壊し等完了日の確認書類(閉鎖事項証明書等)」が該当します。
3.国交省の例文では買主に対する損害賠償請求に関する文言も
買主による譲渡年の翌年2月15日までの工事完了で、売主が空き家特例の適用を受けるための手続の流れは、【参考1】のとおりです。
買主が期日までに工事を行うことを定めた「特約等」の締結や、市区町村への「特約書等のコピー」の提出については、税法上求められていませんが、特約等を未締結の場合は、買主の協力が得られず、買主が譲渡年の翌年2月15日までに工事を完了させない、買主が工事を完了させた後に取得すべき必要書類を交付してもらえないといったことから、空き家特例を適用できないケースが生じる恐れがあり、国交省は、こうしたトラブルを防止するために、市区町村での申請時に確認事項として特約書等のコピーの提出を求めています。国交省ホームページで公表されている特約等の例文では、工事の完了期日、必要書類の交付期日を定める文言に加え、これら期日を守らず空き家特例を適用できなかった場合、買主に対して損害賠償請求が可能とする文言が示されています(【参考2】)。
2024/08/16
![]()
森林環境税
令和6年の税金の話題といえば6月から期間限定で実施されている所得税と住民税の定額減税がありますが、あまり知られていない税金に今年から徴収が開始された森林環境税があります。そこで今回は森林環境税についてお話しします。
1.森林環境税とは
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
※出典:総務省 やさしい地方税
2.創設の経緯
森林には様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や所有者不明の土地の増加などにより経営管理や整備に支障をきたしており、適切な森林整備が課題となっています。このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要性が生まれ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
3.使い道
森林環境譲与税は市町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされており、都道府県・市町村はインターネット等を利用してその使い道を公表しなければならないとされています。
4.納税義務者
森林環境税の納税義務者は、国内に住所を有する個人となっています。
なお、以下の者については森林環境税が課されません。
|
個人市県民税の均等割・所得割が課税されない者 |
■生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 |
|
■前年中の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する者 障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親 |
|
|
■前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の者 ・同一生計配偶者および扶養親族がいない者:45万円 ・同一生計配偶者または扶養親族がいる者: 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族(※)+本人)+21万円+10万円 |
※この場合の扶養親族とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の者を含みます)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者が該当します。
5.令和6年度以降の個人市県民税均等割と森林環境税
平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき各年度分の税額が1,000円(市500円、県500円)加算されていましたが、令和6年からはこの加算措置がなくなり、新たに森林環境税(年1,000円)が導入されました。
2024/07/10
![]()
相続登記の申請義務化
相続した土地・建物の登記はお済みでしょうか。不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。改正法は遡及して適用されるため、今後不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続して現時点で名義変更をしていない方も、相続登記をしなければなりません。今回は相続登記の申請義務化について、お話しさせていただきます。
1.相続登記の義務化の背景
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
2.制度の概要
◆相続登記の義務化は令和6年4月1日開始
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
◆不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
◆過去の相続分も義務化の対象
令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
3.相続登記の義務化と罰則
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
4.相続登記の申請義務化 対応フローチャート
〈出典:法務省のサイト「相続登記の申請義務化特設ページ」〉