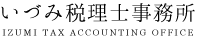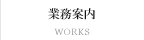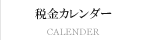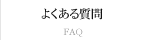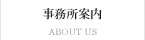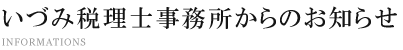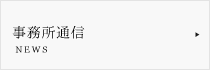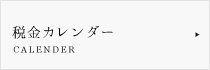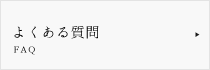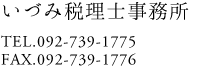2023/01/13
![]()
◆2023年度税制改正大綱 NISA拡充
Ⅰ.NISA(少額投資非課税制度)とは
NISAとは、個人の資産運用を後押しし、家計の資産を「貯蓄」から「投資」に振り分けることを目的とした制度です。これまで投資枠や投資可能期間は限定的でしたが、2023年度税制改正により拡充および恒久化されました。
Ⅱ.改正前
現行NISAには、次の3つの種類がありますが、いずれも期限付きの措置で資産の購入額に上限が設けられていることが課題となっていました。
① 一般NISA
株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できる
② つみたてNISA
一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できる
③ ジュニアNISA
株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できる
出典:金融庁
Ⅲ.改正内容
(1) 恒久化
これまでNISAの非課税保有期間には上限がありましたが、改正により期間は撤廃、非課税保有期間は「無期限」となりました。恒久化になるのは、2024年1月1日以降です。
(2) 「新NISA」の創設
これまでNISAは「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類でしたが、かねてからジュニアNISAについては2023年末で終了することが決まっています。
加えて、2023年度税制改正により一般NISAとつみたてNISAを1つにまとめ「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が設けられることとなりました。それぞれの年間投資上限額は、次の通りです。
•つみたて投資枠:120万円
•成長投資枠:240万円
つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能のため、年間最大360万円まで投資できます。ただし、生涯非課税額には1,800万円(内、成長投資枠1,200万円)の上限があります。
2022/12/23
![]()
令和4年12月1日から、スマホアプリで国税の納付が可能となりました。国税の納付手段を確認しつつ、スマホアプリ納付の概要をご案内します。
1.国税の納付手段
国税は、申告した納税額をその申告に係る納付期限までに自ら納付しなければなりません。下表Aの中から自ら選択して納付手続を行います。
2.スマホアプリ納付
国税の納付手続のうち、令和4年12月1日からスタートした、新しい納付手段です。
(1)利用できるスマホアプリ
●PayPay
●d払い
●au PAY
●LINE Pay
●メルペイ
●Amazon Pay
(2)特徴
●一度の納付での利用上限30万円※
※利用するアプリの設定上限により利用可能額が制限される場合あり
●決済手数料不要
●事前の手続不要
●領収証書は発行されない
クレジットカード納付とは異なり、決済手数料が不要な点が特徴の1つといえます。また、電子納税のような事前の手続が不要な点は利便性があります。
(3)手続の流れ
① 国税スマートフォン決済専用サイトにアクセス
●e-Taxを利用して申告した場合
メッセージボックスに格納される受信通知からアクセス
●国税庁サイトからアクセスする場合
「スマホアプリ納付の手続」ページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」からアクセス
② 納付手続
《ご利用に当たっての注意事項》
・アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に残高チャージが必要です。
・領収書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄税務署窓口で納付ください。
・ポイントの付与については、決済サービスによって異なります。
・法人の税目を個人が立替払いした際にたまったポイントは給与課税される恐れがあります。
2022/11/15
![]()
ふるさと納税の受入総数について総務省の公表によると令和3年度は8,302億円となり、平成20年のふるさと納税導入後、最も多い金額となりました。
今年も残すところわずかとなり、ふるさと納税の駆け込み寄付が増える時期となりましたので、ここで改めてふるさと納税についてご紹介します。
1.ふるさと納税の概要
(1)ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限あり)。
(2)摘要方法
ふるさと納税は原則、確定申告を通じて適用されます。ただし、確定申告をする必要がない方で、ふるさと納税の寄付先の自治体数が5団体以内の場合には、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になるワンストップ特例制度が適用できます。総務省の公表によれば、令和3年度のワンストップ特例適用者は375万人で、ふるさと納税をした人の5割強でした。
|
|
ワンストップ特例制度(注1) |
確定申告 |
|
対象者 |
確定申告が不要な給与所得者であり、かつ、1年間でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方 |
ふるさと納税以外の確定申告が必要or1年間のふるさと納税の寄付先が6自治体以上の方 |
|
手続 |
ワンストップ特例申請書と本人確認書類を各自治体に提出 |
確定申告書に証明書(注2)を添付して税務署に提出 |
|
期限 |
ふるさと納税を行った翌年の1月10日まで |
ふるさと納税を行った翌年の確定申告期間 |
(注1)ワンストップ特例制度では住民税からのみ控除されますが、控除される金額の合計は確定申告をする場合と同じです。
(注2)証明書とは、寄附金受領証明書or特定事業者(注3)が発行する年間寄付額を記載した寄附金控除に関する証明書です。
(注3)特定事業者とは、国税庁長官により指定を受けた一定の者を言い、さとふる、ふるなび等の業者がおり、一覧が国税庁のサイトで公表されています。
(3)12月にふるさと納税をする場合の注意点
12月にふるさと納税をする場合には自治体の受領日に注意が必要です。年内にふるさと納税を行っても自治体の受領日が年をまたいでしまうと寄付金額がその年の所得からではなく翌年の所得から控除されることになってしまいます。そのためその年の所得から控除を受けようとするのであれば、12月31日までに入金完了となるようにふるさと納税を行う必要があります。入金方法としては、自治体やふるさと納税サイトによって異なりますが駆け込みで行う場合は、決済完了日が入金日となるクレジットカードやスマホ決済が決済サービスのポイントも貯まるのでおすすめです。
(4)ふるさと納税の返礼品は課税対象になるのか
ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税対象になります。但し、一定金額までのものであれば税金はかからないことになっています。そのため多くの方は結果として税金はかかりません。
2.ふるさと納税の対象となる地方団体の指定、取消しについて
地方公共団体がふるさと納税制度の対象となるためには総務省から指定を受けるのですが、指定期間は毎年10月1日から翌年9月30日までです。10月1日以降に寄付する場合にはその地方公共団体が指定されているかの確認もしておいた方がよいでしょう。
2022/10/13
![]()
消費税のインボイス制度が開始される令和5年10月1日まで残り1年をきりました。そこで今回はインボイス制度の開始までに決定し、準備しなければならないことをご案内させていただきます。
1.インボイス発行事業者の登録要否の決定
インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。現在、免税事業者の方であっても、事業の内容などに応じて、登録を受けるか検討ください。
□売上先がインボイスを必要とするか
・消費者や免税事業者、簡易課税制度選択の課税事業者である売上先は、インボイスを 必要としません。
□登録を受けた場合・受けなかった場合について
・登録を受けた場合、売上先が求めたときはインボイスを交付する必要があります。
・現在免税事業者であっても、登録を受けると課税事業者として申告が必要です。
・登録を受けている間は、基準期間の売上高が1,000万円以下となっても免税事業者となることはなく、課税事業者として申告が必要となります。
・登録を受けなかった場合、インボイスを交付できませんが、売上先は、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合(80%・50%)が控除できる経過措置が適用できます。また、登録を受けない場合でも、インボイスに該当しない請求書等は交付できます。
□登録を受ける場合は、登録申請書を提出
・令和5年3月31日までに申請すると、制度開始までに登録が間に合います。申請は、書面もしくはe-Taxで行います。
2.インボイス制度への事前準備
売手:インボイス発行事業者
買手:仕入税額控除を適用する消費税課税事業者(簡易課税制度を選択適用している事業者を除く)
〈準備が必要な項目の例〉
免税事業者への対応
免税事業者からの仕入れは納税額が膨らむことが懸念されます。交渉を予定されている場合は、次の点にご配慮ください。
・インボイス発行事業者となるよう強要することはできません。
・納税相当額の値引きを強いることも独占禁止法の観点からお控えください。
編集後記
今回はインボイス制度の準備について紹介させていただきましたが、詳細について、ご不明な点があれば担当者までご連絡ください。
インボイス発行事業者の登録情報は、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)でも確認が可能です。
2022/09/09
![]()
近年、日本各地において災害が頻繁に起きており、先日も台風11号が九州に接近するなど災害が多い状況です。そこで今回は災害に関する税務上の取り扱いについてご紹介させていただきます。
1.所得税の措置
災害によって住宅や家財に損害を受けてしまったときに利用できる制度として、災害減免法と雑損控除があります。その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合には、納税者の選択によりどちらか有利な制度を選べます。
(1)災害減免法
地震や台風、火災などの災害により住宅や家財に損害が生じたときに所得税を減免することを定めたもので、対象資産は自己またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が48万円以下である者が所有する住宅または日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣類、書籍その他の家庭用動産となります。別荘、書画、骨とう、娯楽品等の日常生活に必要でないと思われるものは含まれません。
適用要件は家財の損害金額が時価の2分の1以上で、かつ、その年の所得金額が1,000万円以下の場合となります。具体的には以下のようになります。
|
所得金額の合計 |
軽減又は免除される所得税の額 |
|
500万円以下 |
全額 |
|
500万円を超え750万円以下 |
2分の1 |
|
750万円を超え1,000万円以下 |
4分の1 |
なお、災害減免法の適用を受けるには申請が必要となり、確定申告書等に適用を受ける旨と被害の状況および損害金額を記載して、所轄の税務署長に提出する必要があります。
(2)雑損控除
地震等の災害、盗難もしくは横領により所有する資産が損害を受けたとき、一定の計算式で算出された金額を所得から控除する仕組みのことです。対象資産は災害減免法とほぼ同様となります。
控除できる金額は次の計算式のうちいずれか多い方の金額です。
① (損害金額(注1)+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
② (災害関連支出の金額(注2)-保険金等の額(注3))-5万円
(注1)損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注2)災害関連支出の金額とは、次のような支出をいいます。
① 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
② 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
(注3)保険金等の額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます
2.法人税の措置
(1)災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
① 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
② 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③ 土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(2)復旧のために支出する費用
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」という)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分は次のようになります。修繕費と区分されるものは損金の額に算入されます。
|
内容 |
区分 |
|
被災資産についてその原状を回復するための費用 |
修繕費 |
|
被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用 |
修繕費 |
|
被災資産について支出する費用(上記2つに該当するものを除く)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合 |
修繕費⇒ 30%相当額 資本的支出⇒ 残額 |
編集後記
今回は災害時の税務上の取扱いについて紹介させていただきましたが、これ以外にも税務上の取扱いはございますので、ご不明な点があれば担当者までご連絡ください