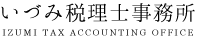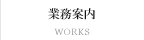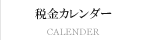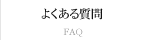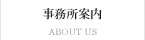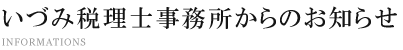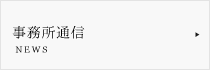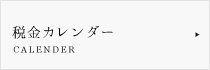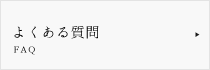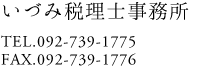2025/04/14
事務所通信4月号
![]()
今回は、ご存じの方も多いと思いますが今一度「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」についてお話しします。
1.少額減価償却資産の特例とは
少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を、平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などをして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、事業年度あたり合計300万円を限度に即時償却(全額損金の額に算入)することができる制度のことを言います。
2.適用対象法人
少額減価償却資産の特例の対象となる法人は中小企業者等です。この場合における中小企業者等とは、大規模法人の支配を受けていない資本金1億円以下の青色申告法人で、常時使用する従業員数が500人以下の法人であるなど、一定の法人等を指します。法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定は原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況によるものとされます。
3.適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、中古資産であっても対象となります。
ただし、この適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数を生じたときは、これを1ヶ月とします)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主な事業として行われるものは除きます)の用に供したものが除かれます。
4.判定のポイント
(1)消費税の経理方式
取得価額が30万円未満とは、消費税の経理方式が税込であれば税込で、税抜であれば税抜で判断します。
(2)他制度との選択
①この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。ただし、IT導入補助金など法人税法上の圧縮記帳との併用は可能です。
②取得価額が20万円未満であれば3年間の均等償却(一括償却資産の損金算入)を選択することができる他、10万円未満であれば少額の減価償却資産として損金とすることができます。これらのいずれかを選択した場合は、償却資産として固定資産税の対象とはなりませんが、少額減価償却資産の特例を適用した場合には、償却資産として固定資産税の対象となります。そのために固定資産税との兼ね合いも考えて他制度との選択をする必要があると言えます。
(3)比較
| 対象 | 取得価額 | 償却方法 | 固定資産税 |
| 中小企業者等のみ | 10万円以上
30万円未満 |
全額損金算入
(即時償却) |
課税 |
| 全ての企業 | 10万円以上
20万円未満 |
3年間で均等償却 | 非課税 |
| 全ての企業 | 10万円未満 | 全額損金算入
(即時償却) |
非課税 |
5.手続き
この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書に少額減価償却資産の取得に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要となります。